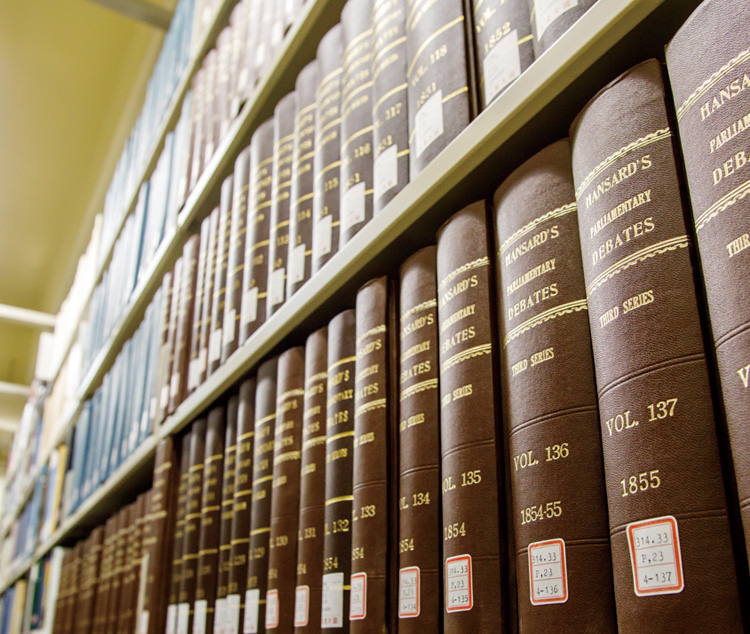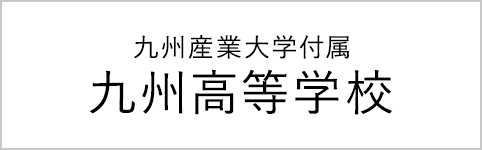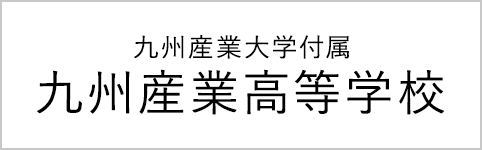8月7日(木)、出水市ツル博物館クレインパークいずみで、博士前期課程全研究科共通科目「プロジェクト実践演習A」を受講する大学院生6名が企画したワークショップ「つくってわかる!LaQで学ぶむしのからだ」を、経済学部環境経済学ゼミナールに所属する学生5名と共同で開催しました。
同科目では、生物多様性の「価値」について、経済学・生態学・芸術学の各分野の視点から、多面的な評価を追求する学修を行っています。
テーマは「知育ブロック『LaQ(ラキュー)※』を用いて昆虫の基本構造を学ぶ」。当日は、大人46人、小中学生59人、幼児31人の計136人が参加しました。工作は、ヨシリツ株式会社のファシリテーター「LaQハカセグリーン」の協力を得て、カブトムシまたはクワガタムシのいずれかを作成。工作後は、完成作品を用いて「カブトムシやクワガタムシのおなかはどこか?」を考えてもらい、参加者は頭・胸・腹の基本的な体の構造について理解を深めました。
同ワークショップを企画した芸術研究科2年の魚住楓さん(城東高校)は「子どもたちの身近なおもちゃであるLaQを使った造形遊びを通して、楽しみながら昆虫の体のつくりを知ってもらうことを目的に取り組みました。アドバイスを行うだけでなく、参加者のニーズに合わせた知識の提供や指導を行うことで、楽しい学びの時間になったと思います。また、当日に向けて、大好きな虫の一つである絶滅危惧種『タガメ』の捕獲脚をモチーフにしたLaQ作品を準備しました。タガメの捕獲脚は、自分より大きな魚や蛇までも捕らえるほど強力で、そのかっこよさや魅力、貴重さを伝えられるよう、造形やキャプションを工夫して制作しました。その結果、参加者が展示を見てタガメに興味を持つ様子を実際に目にすることができ、大好きな生き物の知識普及に貢献できたことをとても嬉しく感じました」と振り返ります。
※LaQ(ラキュー)は、たった7種類のパーツから平面・立体・幾何学体とあらゆる形に変化するパズルブロック

【大学院・経済学部】