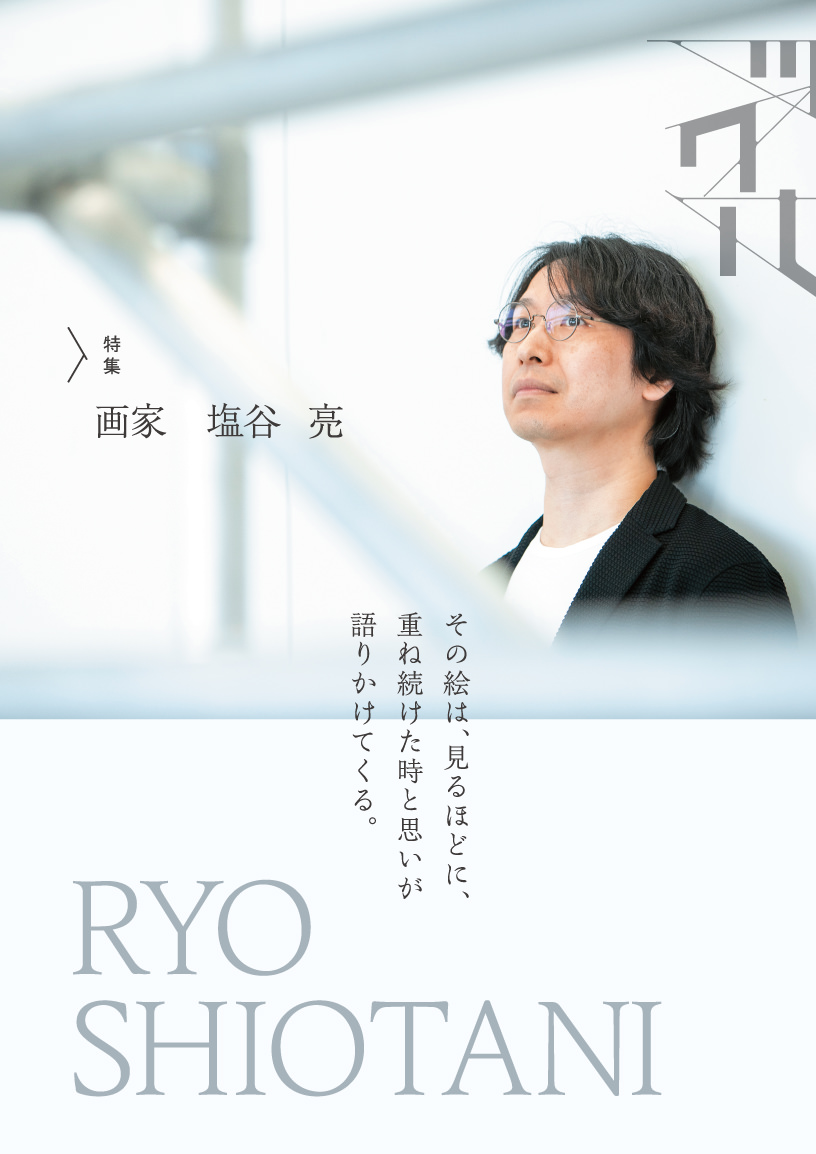- HOME
- 特集 画家 塩谷 亮
原点は、2年間続けた
小学校の絵日記。
子供の頃から絵を描いたり、ものを作ったりするのが好きでしたが、小学校3、4年生の時の担任が宿題を出さない代わりに、毎日、絵日記を提出させる先生だったんです。その日の出来事を文章で書いて、それを絵で再現するということを2年間やりました。友だちはみんなイラスト風の挿絵だったんですが、私は、たとえば自分の着ていた服などを克明に描いていました。靴下の柄までちゃんと再現したり。当時から写実志向というか絵で記録するという考え方が自分の中にあったんだと思います。図画工作よりも、理科で観察画を描くのが好きだったんですよ。動物とか植物が大好きだったので、自分の部屋はペットショップみたいに水槽が並んでいました。そこに昆虫から爬虫類、両生類まで飼っていて、その可愛さを記録したくて一生懸命観察画を描いていました。
朝の光を浴びる石膏像が
「感動」を教えてくれた。
でも、好きなものを観察して記録して上手に書けたら満足というのは趣味の範囲です。美術大学を目指そうと美術予備校に通った時、先生から「君の絵は上手いけど感動がない」と言われてしまいました。「感動って何だろう?」と、すごく考えました。高校に通いながらだったので美術予備校へ行くのは夜だったんですけど、ある日曜日の朝、忘れ物を取りに教室へ行った時、朝の光を浴びて輝く石膏像を見て息を呑むような美しさを感じました。普段、蛍光灯の下で見ていた石膏像とは全く違う、教室の空気を一変してしまうほどの存在感に初めて感動しました。同じ対象を描くにしても、光やシチュエーションがとても大切。そこから生まれるドキッとした気持ちを表すことが大事なんだなと実感しました。
絵一筋の4年間。
しかし、大学院進学を失敗。
武蔵野美術大学に入学してからは絵一筋の毎日でした。親に学費を払ってもらっていましたし、大学の施設や先生のアドバイスを有効に使わなければというのもあって。サークル活動もせず、みんなが学生生活をエンジョイしてる中、そそくさと帰って家でも絵を描いていました。大学4年間、どちらかというと優等生扱いされていたのですが、大学院への進学試験は落ちたんです。あと2年間大学で学ぼうと思っていたのに、突然作家として社会に出なければならなくなりました。挫折感もあったのですが、急展開のなか自分を顧みて作家としての在り方を考えたのは、私にとってよかったと思っています。大学院の審査に関わった先生がポロッと「君はもう早く外へ出て活動した方がいいんだよ」と言ってくれたので、ちょっと前向きにもなれましたし(笑)。
コンクールで認められなくても
自分の絵を信じて描き続ける。
大学を出て、自分の絵を美術界に認知させようと全国の絵画コンクールに手当たり次第出品しました。グランプリは無理でも入選はできるだろうくらいの自信はあったのですが、3年間出し続けて、なんと全て落選。当時写実絵画は保守的な表現と見られやすく、コンクール向きではありませんでした。審査は一瞬ですが、私の絵はじっくり見ていると魅力がにじみ出てくるような絵だと自覚していたので、仕方ないなぁと思っていました。コンクールの傾向に合わせて表現を変える作家もいるのですが、私はそういうタイプではないですし。ただ、そんな私の地道な活動を応援してくれる画商の方と出会うことができました。「ブレないところが塩谷君の良いところだから、焦らずにやっていこう!」とアドバイスをいただきつつ、それ以降は個展による発表に軸足を移していきます。展覧会のたびに評判を呼び、少しずつ画家として生活できるようになりました。
瞬間を切り取るのではなく、
描いた時間と思いを重ねていく。
写実絵画は、写真とは何が違うのか?という問いをよく耳にします。写真は一瞬を切り取るものです。私の絵画は、目で見て実感した手ごたえを一つ一つ、痕跡のように刻んでいきたいという感覚があるんです。一枚の絵を描くのに、毎日毎日、1ヶ月ぐらいかけて描くんです。そうすると、その日の天候によっても対象物の見え方は違っているし、描いている自分の心も高揚したり、落ち込んだり変化していきます。その日その日の思いをレイヤーのように重ねていく感じです。描き上がった絵は、一瞬の風景のようですが、実は、そこには長い時間が凝縮されているんです。
自然由来の画材を思い通りに
使いこなせる知識と技法を。
油絵は、木や布の上に、土や鉱物に植物油を加えて練り上げた絵の具で描くものです。自然由来の画材を思い通りに使いこなすためには、知識や技法がとても大切になってきます。今はチューブ絵の具を買ってきて絞り出せば誰でも描ける時代ですが、それがなかった時代の画家たちは、ひとつの色をつくるのに、まず顔料を見つけてきて、それを粉にして何と混ぜれば求める色になるのか、乾燥をゆっくりさせるためにはどうすればいいか、逆に早めるにはどうすればいいか、錬金術みたいなことをいろいろやった上で、自分のイマジネーションを絵に定着させていました。そのプロセスは、今もとても大切だと思っています。先ほども話しましたけど、私の絵は毎日思いを重ねるように描いていきます。油彩画は、不透明なもので塗りつぶしていくのではなく、常に下の層がほんのり発現している感じがあるんです。ふわっとベールをかけたように、前日に描いた絵が見えてくるんです。そういう油彩における透明性は、さらに研究していかなければと考えています。
AIの進化に期待するのは、
ルネサンス時代のラファエロ。
AIが、すごい勢いで進化しています。私がAIを利用して描くことはないと思いますが、ちょっと面白いなと期待している部分もあります。画像生成AIは、さまざまな情報を学習、融合させていくのですが、そこにオリジナリティという課題が問われています。人間の創作におけるオリジナリティも、人生で蓄積された知見が融合して生まれてくるものだと思います。例えば、ルネサンスの三大巨匠の一人にラファエロという画家がいます。この人は同じく三代巨匠のあと二人、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロを尊敬していて、彼らの様式や技法を会得し、融合させた表現で爆発的に人気が出ました。AIが得意とする学習と分析、そして融合によって、今後、どのような可能性が生まれてくるのか、とても興味を持っています。
異分野とのコラボで拓く
新たな表現の可能性。
九芸は、分野の壁を越えて学び合うことを大切にしていますが、それはとても良いことだと思います。私の場合、展覧会などを企画されると、どうしても写実絵画のグループ展を組まれてしまうことが多いんです。同じジャンルによる展覧会も楽しいのですが、何か違う分野とコラボできないかといつもアンテナを張っていました。そこで、テレビを見ていて、とても興味を持ったのが左官職人の久住 有生(くすみなおき)さんです。アートの分野で活動を模索していると聞いて、私から「二人で展覧会を開きたい」とオファーしました。久住さんの表現は抽象的なのですが、素材が土や砂、藁のような繊維など、自然物だけでつくられているんですよ。 同じく自然をテーマにした私の絵と彼の作品を交互に並べて展示すると、それぞれの素材と表現に対する意識が浮かび上がり、これまでにないコラボレーション展ができたと思います。
中高生の時に好きだったことを、
突き詰めていくことが大事。
写実絵画は、写真とは何が違うのか?という問いをよく耳にします。写真は一瞬を切り取るものです。私の絵画は、目で見て実感した手ごたえを一つ一つ、痕跡のように刻んでいきたいという感覚があるんです。一枚の絵を描くのに、毎日毎日、1ヶ月ぐらいかけて描くんです。そうすると、その日の天候によっても対象物の見え方は違っているし、描いている自分の心も高揚したり、落ち込んだり変化していきます。その日その日の思いをレイヤーのように重ねていく感じです。描き上がった絵は、一瞬の風景のようですが、実は、そこには長い時間が凝縮されているんです。
塩谷 亮 しおたにりょう |
|
| 1975 | 東京都生まれ |
| 1998 | 蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業 |
| 2008 | 文化庁新進芸術家海外派遣研修員(~2009 イタリア) |
| 2010 | 武蔵野美術大学、九州産業大学、日本大学などで教鞭をとる。 |
| 〈主な個展〉 | |
| 2002 | 塩谷亮油彩展(銀座松坂屋) |
| 2004 | 塩谷亮展(彩鳳堂画廊、名古屋松坂屋、大阪髙島屋ほか) |
| 2008 | 静謐な光 塩谷亮油絵展(日本橋三越) |
| 2010 | 文化庁在外派遣研修報告展(彩鳳堂画廊) |
| 2017 | 塩谷亮展 ― 瞬く間にひそむ叙情を求めて(Bunkamura Gallery) |
| 2022 | 塩谷亮展 ― 日常にある脈動(Gallery Suchi) |
| 〈著書〉 | |
| 2004 | 塩谷亮作品集2000-2004(彩鳳堂) |
| 2015 | 油絵 明暗と技法(共著/グラフィック社) |
| 2017 | 塩谷亮画集(求龍堂) |