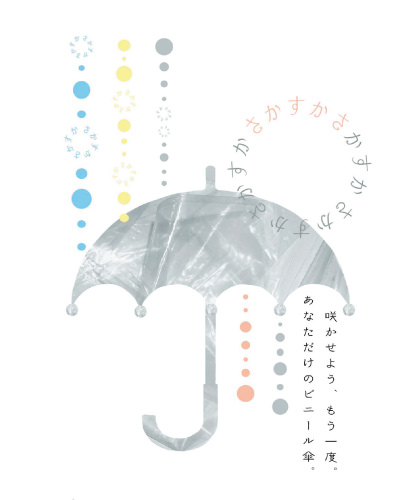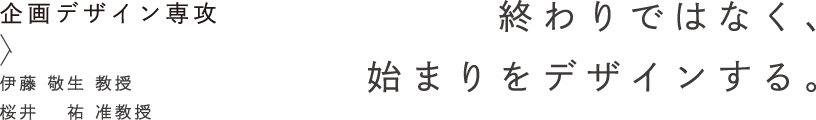- HOME
- 新しい「ツクル」が始まる!九芸新専攻特集3企画デザイン専攻
建築家ではなく、庭師のように考える。
桜井)
今回の芸術学部のリニューアルにあたり、ソーシャルデザイン学科のコンセプトを考えることになりました。いろんな表現を模索する中で私はブライアン・イーノ(※)が「ストリートのミッションに関するデザイン・プリンシプル」で掲げていた「終わりではなく、始まりをデザインする」という言葉がしっくりきたんです。この言葉についてイーノは「庭師のように考えよ」とも言い換えています。建築家は建物を完成させるのがゴールですが、庭師は、今後どのように生態系がつくられていくか、10年後、20年後、へたすれば100年後とか想像しながら最初のお膳立てをする仕事なんですね。その視点から考えると「企画を生み出すこと」は「始まりをデザインすること」にも等しいんじゃないかと。

伊藤)
地域ブランディングでいうと、でっかいクリスマスツリーを作り飾り立て、時が過ぎたら捨てるみたいなプロジェクトが多い気がします。何千回バズったとか、数字の結果だけで成功を評価するような。でも本来、地域には歴史という根っ子があって、その上に幹が育ち葉が茂り、そこに実が成って人々が豊かになるよう生態系をつくっていくものが企画デザインだと思います。まさに、注力すべきは「始まり」なんです。
自分に問いかけ、自分ごととして問題を見つける。
桜井)
企画を生み出す上では、問題解決の前に問題を提起する必要があるわけですが、学生と面接していると「人口減少をなんとかしたい」とか「海洋ゴミをなんとかしたい」とか、すごく大きな社会課題を持ってくる人が多いと感じます。ただこれらって、ほとんどの場合は誰かが言っていたどこかから借りてきた課題であって、彼、彼女たちの地に足のついた生活圏内から出てきている課題じゃないんです。そうした“借りもの”の課題ではなく、学生自身が周りを見渡し、自分の視点で発見した社会の問題点に取り組むことを大切にしたいですね。
伊藤)
私の講義では、「なんでやるの?」「どうしてやるの?」といった禅問答みたいな問いかけが多いんですが、それを常に自分の中に持っていないと、本来の目的が薄れて手法や手段が目的になってしまうんです。あれ?これを作るためにやってるんじゃないよね?何のためにつくるんだっけ?いつだって、そこに立ち返らないといけません。そして、ぜんぶ自分ごとになっていることが大事。自分にとっての何を問うのかによって、企画への踏み込み度合いは段違いに異なってきます。人生においても、いちばん大事なことです。たとえば、家庭の中の子育てだって同じですよね。
チーム力、編集力で課題を解決する。
桜井)
九芸の中の役割分担でいうと、企画デザインは問題を発見することに注力するわけですが、「どうやって解決するのか?」となったとき、自分だけでは解決できないこともあります。そんなときに頼りになるのが、さまざまな専門性を持っている他学科専攻の学生たちです。グラフィックデザイン、動画、空間演出から工芸まで、いろんなことを学んでいる学生たちがいますし、設備も充実しています。必要なチームメンバーを集めて、いっしょに解決していく。それをできるのが九芸の特長なんです。

伊藤)
九産大ってすぐにチームを作ることができて、必要な技術や知識を実装できる環境なんですよ。コロナ禍で交流にブレーキがかかったこともあったけど、学生たちも、教員たちもフットワーク軽く、いっしょに課題と向き合ってくれます。社会に出て体験することをシミュレーションするのに、こんなにいい場所はないですね。
桜井)
僕自身が編集の仕事をしているんですが、編集者って一人では何もできないんですよ。でも、チームを組めば何でもできる。写真はこの人がいい、デザインはこの人・・・と仲間を集めて、みんなが同じ方向を目指せるようにコンセプトメイキングして協働していきます。
伊藤)
今、ゼロから何かをつくり出すという時代じゃないと思うんです。資源は足りないけど、モノや情報はあふれている。今あるモノやコトを一つひとつ良さや価値を見直し、組み合わせることで新しい創造物が生まれる。まさしく、桜井先生の「編集」的な力が時代的にも求められていると思います。
オランダと同面積の九州に眠る可能性。
伊藤)
今、桜井先生と、九州を縦に南下する学外演習を計画しています。実は九州とオランダはほぼ同じ面積なんですね。だけどオランダは九州の約1.5倍のGDPがあり、ヨーロッパの国々と対等に向き合っている。だったら、九州の中だけで何かを成立させることができるのでは?というテーマなんです。


海洋プラごみ100%の石けんケース「mu」
桜井)
いっそ九州は独立国家になればいいと思っていますよ(笑)。「地方」とひと言で言いくるめられる中には、多種多様な人や歴史・文化、資源があるにもかかわらず、往々にして地方と東京は二項対立で語られますよね。私からすればそのことがおかしい。福岡も東京と比べてどうなのかではなく、もっと広い視野で、たとえば釜山であったり大陸との関係において福岡ってどうあるべきなのか?みたいに意識を変えていく必要があるのではないでしょうか。
企画デザイン専攻で得られること。
桜井)
私も含め、編集者って「何がしたくて、これをやっているのか?」が、人によってちょっとずつ違うんです。たとえば、私の友人は「誰も見たことのない風景を見たい」という願望へのプライオリティがいちばん高く、そのために取材へ行くし、メディアもつくっています。私の場合は「なぜ、こうなのか?」が知りたくて、歴史からアプローチしたり、インタビューしたりしながら、世界の仕組みを解き明かすことに興味の源泉があります。とはいっても企画デザインで学びたい学生みんなが、自分の究極的な目的を言語化できている必要はありません。世の中に対する強烈な好奇心があり、そこへ能動的に関わりたいという思いがあれば大丈夫。共に学び「始まり」をデザインする上で参考になるカリキュラムを提供できると思います。


MARUHIRO BOOK 2010-2020,2021-
伊藤)
今までは言葉に関するカリキュラムがなかったんですよね。素晴らしいアーティストは、素晴らしい言葉を残しているのに。企画デザイン専攻では言葉に関するカリキュラムも設けていて、学びの幅が広がっています。芸術学部を出ても、アートのスペシャリストだけが進むべき道ではないんです。どんな企業にも「企画」という名称が付いた部署がありますし、どんな仕事をするにも企画力は欠かせません。これからの時代を生き抜いていくための力強いツールを企画デザイン専攻で身につけてもらえるはずです。
※ブライアン・イーノ
イギリスの音楽家、音楽プロデューサー。「アンビエント・ミュージック(環境音楽)」の先駆者として知られている。視覚芸術のインスタレーション作品などにも積極的に参画している。