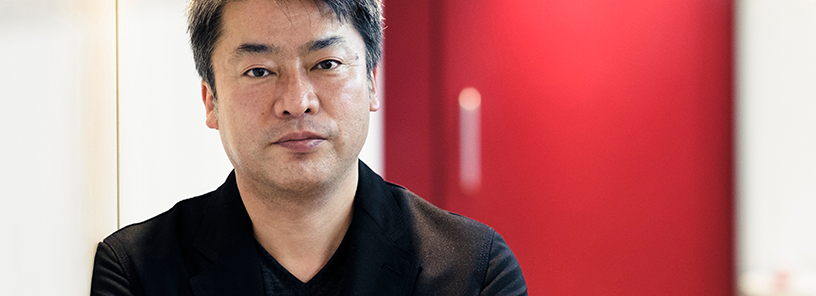「高校は普通科に進みましたが、『美術部を作ってくれ』と先生に直談判した。在学中に、高校文化連盟のロゴデザインの募集があって、運良く僕の作品が選ばれたりしたこともあった。学生時代はテクノポップの洗礼をまともに受けて、そこから派生した音楽や映画、カルチャーに傾倒していった。デザインやコミュニケーションというものに興味を持つようになったのはその頃からかな。」

本格的にデザインを学びたいと、故郷・宮崎から近く、身近だった九芸に進学。学生生活の中心は美術部の活動で、展覧会や催し物の企画などを積極的に行った。「自分よりも絵が上手い同級生がいる」事実から、絵で競争するのではなく、自分が楽しめるカリキュラムに力を入れることを決意。日高さんが絵を描くこと以上にのめり込んだもの。それがデザインであり、広告だった。
「小さな頃から、とにかく人を楽しませたり、驚かせることが好きだった。その延長線上に授業があったという感じ。実習課題なんかも、クオリティや表現は二の次で、どれだけ人に笑ってもらえるか、楽しんでもらえるかという提案しかしなかった気がする(笑)。」
「グラフィックもCMも含めて、90年代は広告が光輝いていた時代。その煌びやかさがまぶしかった」と日高さん。卒業後は外資系のデザイン会社に入社後、宮田識氏率いるDRAFTへ。12年間在籍したDRAFTで、日本を代表するアートディレクター・宮田識氏の仕事に触れたことは大きな財産となった。
「デザインは氷山の一角のようなもの。その下に積み上げる部分がどれだけ大切かを宮田さんに教わった。当時は“ブランディング”なんて言葉もなかったけど、今思えばDRAFTは、どんな仕事でもブランディング的発想を持って取り組んでいたんだ。」
故郷である宮崎県との関わりが深まったのは10年程前から。宮崎県から県内企業へのデザイン指導の依頼があり、パッケージやPOPなどビジュアルデザインに関するアドバイスを行った。そして、2010年に発生した口蹄疫問題で未曾有の危機的状況に晒された故郷。日高さんは宮崎在住の後輩デザイナーと共に、東京ミッドタウンのサテライトスペースを使い、宮崎を応援するパネルを制作。殺処分対象となった10万頭の牛と豚をレイアウトした「10万頭パネル」が大きな話題を呼んだ。
「口蹄疫問題が終息したあとも、ポスターを作ったり、広告を作ったり、宮崎県の仕事を手掛けるようになって。それから県の担当課から、新しいプロモーションのアドバイザーになってほしいという依頼があった。当時、香川県が仕掛けた『うどん県』が大ヒットしていたんだけど、同じような事をやっても二番煎じになる。ユーモアだけを追求するものや、動画の視聴再生回数を伸ばすことを目的にしたくなくて。県全体をくくることができるコンセプトを探す中で行き着いたのが、“ひなた”という言葉。インパクトはないかもしれないけど、ゆったり、じわじわと広がっていく感じが宮崎ならではのプロモーションだと思った。」
「ひなたプロモーション」は現在も続いている。一過性のもので終わらせないために、ずっと残り、波及していくことを大切にした。まさにひなたのようにホンワカとしたブランディング。「その広がり方も宮崎らしい」と日高さんは語る。今後の展望を尋ねた。
「写植の時代からこの世界にいるけど、時代は変わって、今はWebやデジタルの方にコミュニケーションが移行してきているよね。その中でも僕の基準はグラフィックデザインがベースだと思っている。すべてがブランディングという意識でやっている。」
最後に、日高さんなりのエールを送ってもらった。
「大学時代の価値は、時間が有り余る程あるということだよね。怠惰な時間も多かったけど(笑)、今振り返ってみると大事な時間だったんだと思う。そしてやっぱり、好きなことを信じるということが大切だね。」

左)「日本のひなた宮崎県」プロモーションロゴ 中)「日本のひなた宮崎県」ポスター 右)佐土原ナス ロゴ・パッケージデザイン