

スポーツに取り組むことは、私たちの生活にどのような変化を与えてくれるのか。剣道熟練者の目付け※をきっかけにアスリートの効率的視覚システムの研究に取り組み、大学初の実践的トレーニングシステムの構築を行う秋山准教授に話を聞きました。
※目付け=相手の顔、特に目を中心にして、相手全体を見るようにすること
秋山准教授のこれまで
おじいちゃんになぜ負ける?
剣道での疑問が研究の出発点
私は小学1年生から剣道とともに人生を歩み、今も九産大の剣道部で監督をしながら学生たちと道場で汗を流しています。研究では、スポーツ心理学の手法を用いて長年の修練期間で熟達化される剣道エキスパートの視覚スキルに着目した研究を行っています。そのきっかけは「生理機能が低下しているおじいちゃん剣士に負けてしまう」、その理由が知りたかったからなんです。
武道の経験がない方は、「いくら相手が達人とはいえ、おじいちゃんに負けるわけないでしょ」とおっしゃるのですが、剣道だけでなく武道の世界では「おじいちゃんに負ける」現象はどこででも起きている普通のこと。それが武道の魅力のひとつでもあるのですが、博士課程で学んでいた時に「その謎を解明したい」と考えたことが、研究の出発点となりました。大学で研究をしている人間は、自分の研究分野や専門競技をいかに発信していくかが大事です。日本固有の文化である剣道について、競技としても研究分野としても廃れないよう学術的に発信していくことは、私に与えられた大切な役割のひとつだと考えています。

准教授のプロジェクトについて
直径約4mの円形シアターで
トレーニングシステムを構築
人は加齢とともに生理機能が低下しますが、剣道は熟練期間に応じて技能が向上します。そこに関係する効率的な動きや対応力の秘密は、脳や目に隠されているのではないかと推測しました。でも、競技中の脳活動を測定することは現在のテクノロジーではできません。そこで、視覚に着目して「何を見ているのか」と「どこまで見えているのか」を研究してきましたが、それらをよりリアルに測定できる統制された環境が必要だと感じていました。そんな時、株式会社ピー・ビーシステムズとの出会いがありました。アスリートの視覚研究から得られた知見を応用し、テクノロジー活用による人工的な環境でのトレーニングシステムの構築を目指すことになり、共同で仮想環境下での実験やスポーツパフォーマンス向上のためのトレーニングを研究しています。直径4m程度の円形シアターに12台のプロジェクターで3D映像を投影するシステムを学内に常設し、ゼミの学生たちと実験や新たなコンテンツ制作に取り組み、今までできなかった測定やトレーニング環境を開発しているところです。他の大学にはない九産大だけの設備なので、学生にとって、大きな価値のあるものだと思います。


剣道でもその他のスポーツでも記録や勝敗が重要視されますが、取り組むことで得られるメリットは多数。プレーヤーが行う「見る→考える→動く」といった一連のプロセスは脳活動によるものであり、想像以上に頭を使っていることを学生に認識してもらいたいですね。私が構築していきたいのは、実験や研究に使えるだけでなく、ただ普通に「運動を楽しむ」ことにも活用してもらえるトレーニングシステム。高齢化社会の中で、加齢による認知機能の低下が深刻な課題になっていますが、私たちのトレーニングシステムは高齢者でも使えるものなので、こうしたシステムが世の中にもっと広がって、自分の体力や認知機能のレベルがわかったり、ゲーム感覚で楽しみながら運動ができれば、健康寿命の延伸にもつながっていくのではと期待しています。
今後の活動・目標について
スポーツの多面的な価値を
多くの人に伝えていきたい
今後は、仮想空間を用いたスポーツ指導や学習環境の開発をさらに進め、大学初の実践的トレーニングモデルを構築したいと考えています。スポーツを通じて得られる人間的成長の価値をより多くの人に伝えるために、研究成果の社会還元にも力を入れていきたいです。
スポーツの世界は競争が激しいため、「記録がでない」、「トップ選手になれない」と、若いうちにそのスポーツから離れていってしまう人がたくさんいます。でも、単純に運動することが体に良いだけでなく、私の研究からもわかった「見る→考える→動く」の脳活動の活性化は、例えば「車の運転中にとっさに飛び出してきた歩行者にすばやく反応できるか」といった、日常の判断行動にもつながる大切なこと。自分の強みや弱さと向き合うことで自己成長につながるというメリットもあるので、辞めてしまうのはもったいない。そこで、「なぜこのスポーツをしているのか」、「どんな考えで取り組んでいるのか」という自らの理念をプレーヤーや指導者が言語化して明確にすることで、長期的な視点でスポーツに関われるようにするための研究も進めています。学生たちもそれぞれがプレーヤーであり、将来は指導する立場になることもあるでしょう。教育・研究の両面から支援を行っていけたらと考えています。

-

-
- Q.趣味はなんですか?
- 剣道
小学1年生から今に至るまでずっと続けています
スポーツ観戦も好きです
-
- Q.好きな食べ物は?
- いちご

-
- Q.今、興味・関心があることは?
- 大学でのスポーツはどのように変化していくべきか
九州産業大学公式YouTubeチャンネル
-

子どもたちが
飢えない社会をつくる -

九州の農業を
ロボットの力で支える -

海洋プラスチックについて考える
”きっかけ”を与えたい -

写真を通じて
人と場所のつながりを探求する -

食の安全・安心を追究し、
食品ロスを減らしていきたい -

新しい冷媒技術で
未来の人類を救いたい -

快適で健康的な
居住環境をデザインする -
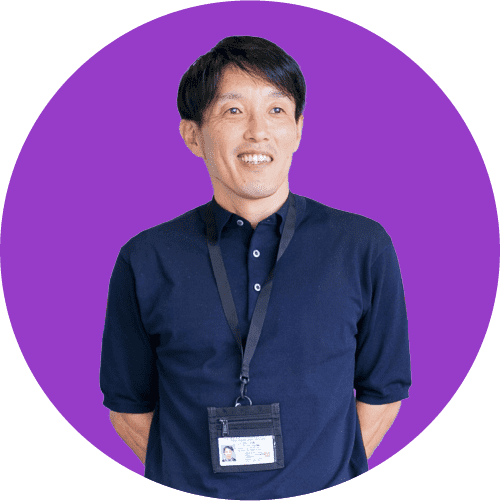
スポーツを続ける
「明確な効果」を広めたい -
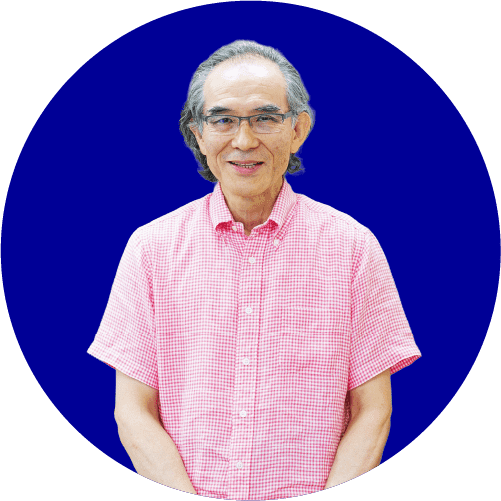
個人が、楽しみながら
「水害対策」を行う時代に -
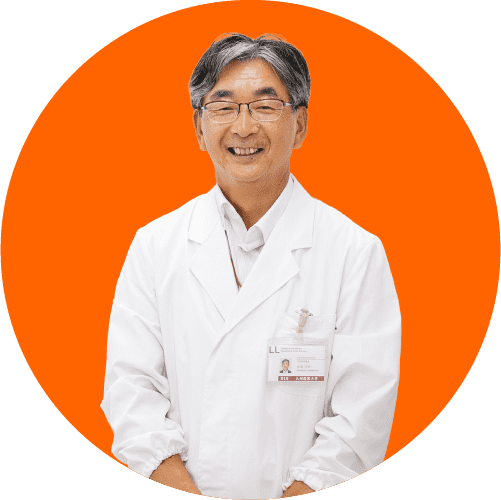
ラーメン店のおいしさを
お土産品でも再現したい -
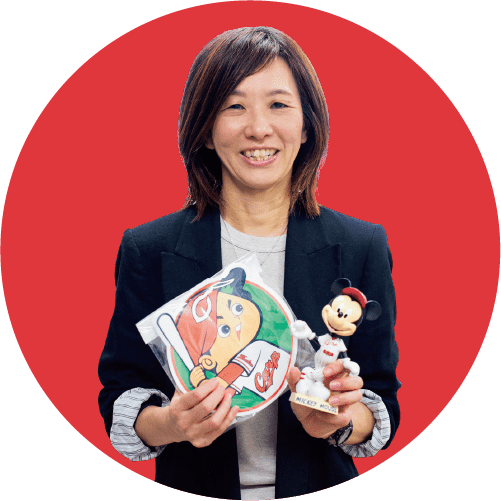
日本の観光を
もっとおもしろく変えていく -

暮らしも人間性も豊かになる
「言語学」の魅力 -
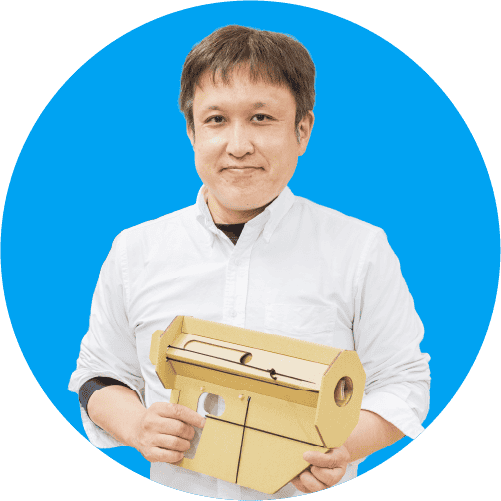
「工作」と「遊び」の力で
地域の課題を解決したい -

新興国の経済研究で
日本の経済を輝かせる -

九州から世界への挑戦を
研究を通して応援したい



