

2023年4月に開設された「グローバル・フードビジネス・プログラム」では、フードビジネスを通して地域を活性化させたり、グローバル化するフード産業で活躍できる人材を目指してさまざまな活動に取り組んでいます。今回は、農産加工に深く精通し「ベトナムライチプロジェクト」に携わった尾崎教授にインタビューしました。
尾崎教授のこれまで
自分自身の体験をもとに
フードビジネスを伝えたい
もともとは都市開発や都市計画のコンサルティング会社に勤め、農村漁村に関する仕事に携わっていたんです。でも、そこでは地域との交流は一時的なもの。「もっと深く地域の人々と関わっていきたい」との思いから、33歳のときに独立して創業。それ以来、農水産加工や農水産加工コンサルティングの仕事を行ってきました。

九産大には昨年着任し、令和5年4月に新設されたばかりの「グローバル・フードビジネス・プログラム(GFBP)」を担当しています。フードビジネスを通して世界で活躍する人材を育成するというのは、おそらく全国でも新しい試み。私が20年以上自分の会社で行ってきた「農業や漁業の生産者が進める付加価値形成に対して、製品づくりや商品開発、製造手順の構築などで支援していく取り組み」での経験を学生たちに伝えていけたらと考えています。

「ベトナムライチプロジェクト」について
ベトナムの高品質ライチ
加工技術普及の取り組みも

私は朝倉市に食品加工ができる設備を持っており、例えば地元の農家の方から持ち込まれた野菜をジュースなどの加工品にし、それをどうプロモーションしていくのかという活動を日々行っていますが、国内だけでなく海外の産地での取り組みも行っています。そのひとつが、昨年からスタートしたベトナムのハイズオン省フィンラップ村で行っている「ベトナムライチプロジェクト」です。




この村のライチは品質が高いことで有名で、ほとんどが海外に輸出されます。5~7月が旬でたくさんのライチが収穫されているのですが、朝から気温が35度ぐらいという厳しい暑さの中、日本のように保冷の設備が整っていないため、収穫したライチを良い環境で保管することができません。すぐに売ることができなければ、せっかく収穫してもどんどん傷んでしまう一方。全体の3割程度のライチが廃棄されてしまっているという問題を解決できるよう、「収穫したものを現地でそのまま加工することはできないか」と相談を受けたのがきっかけでした。
現地で搾汁して果汁にし、それをきちんと保存して1年間かけて販売していく方法を提案し、廃棄していたライチをおいしいジュースにすることに成功。当初は日本への輸出を考えていましたが、大切なのは地産地消です。ベトナム国内での売り方を模索していきました。

今後の活動・目標について
実践的な学びを通して
食に関する知識を豊かに
私がこうした取り組み・研究を行っている理由は、農業、水産業、畜産業など食料生産に従事する人々の暮らしを支えることが、いまの子どもたちが将来的に飢えない社会をつくる上で必要不可欠だと考えているからです。未利用の素材をより良く生かすことは、食料の有効利用になるだけでなく、新たな食文化を生むきっかけにもなります。さらに、地域づくりの観点では、こうした活動によって新たな経済や仕事を生み出し、その地域に賑わいをもたらす効果が期待できるのも魅力です。

誰の隣にも農業や水産業、畜産業はあるはずなのに、食べる人と実際の生産の現場って距離があるんですよね。それを埋めていきたいと考えています。GFBPで学ぶ学生たちには、生産者の方とのつながりを持って欲しいので、これからさまざまな場所でフィールドワークを実施していきます。また、3年次には全員でハワイ大学カピオラニ・コミュニティカレッジを訪問し、ハワイのフードビジネスを学び、郷土料理のプロモーション戦略や食品加工の現場に触れる予定です。
こうした学びを通して、学生たちには素材の旬のこと、産地に関する知識、それらをおいしく食べるための料理法、どう提供したら喜ばれるのかなど、食べ物に関するあらゆる知識を身に付けてもらえたらうれしいですね。国の食料政策は時代に合わせて変化していますが、身近な食に関わる施策と現場の生産者の考えに触れて、これから世の中の食で何が求められるか、学生と一緒に学んでいきたいと考えています。

-

-
- Q.趣味はなんですか?
- 料理と食品加工。仕事でもあり、趣味でもありますね。
-
- Q.好きな食べ物は?
- 魚料理とジビエ肉料理
-
- Q.今、興味・関心があることは?
- 英会話! 学生を率いていく海外研修があるため。
-
- Q.「九産大生」の印象は?
- 素朴で朗らかな学生が多いと思います!
九州産業大学公式YouTubeチャンネル
-

子どもたちが
飢えない社会をつくる -

九州の農業を
ロボットの力で支える -

海洋プラスチックについて考える
”きっかけ”を与えたい -

写真を通じて
人と場所のつながりを探求する -

食の安全・安心を追究し、
食品ロスを減らしていきたい -

新しい冷媒技術で
未来の人類を救いたい -

快適で健康的な
居住環境をデザインする -
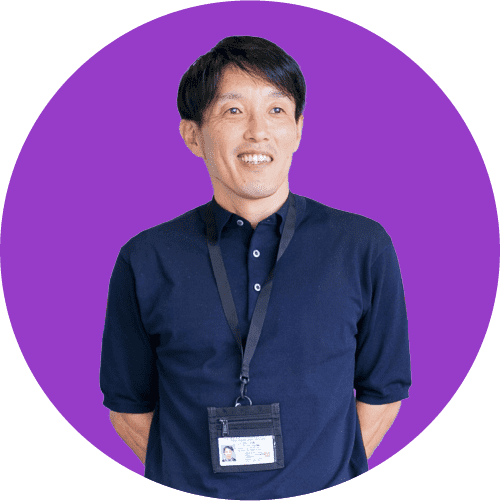
スポーツを続ける
「明確な効果」を広めたい -
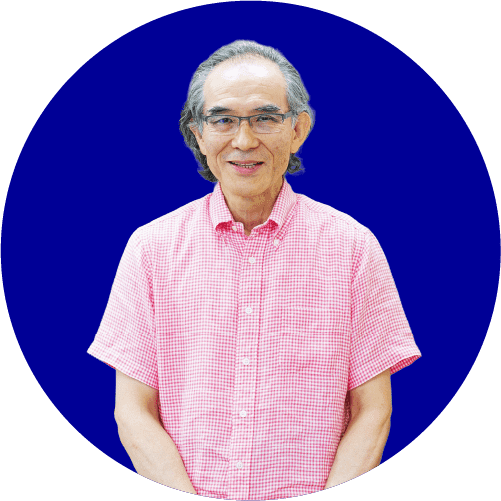
個人が、楽しみながら
「水害対策」を行う時代に -
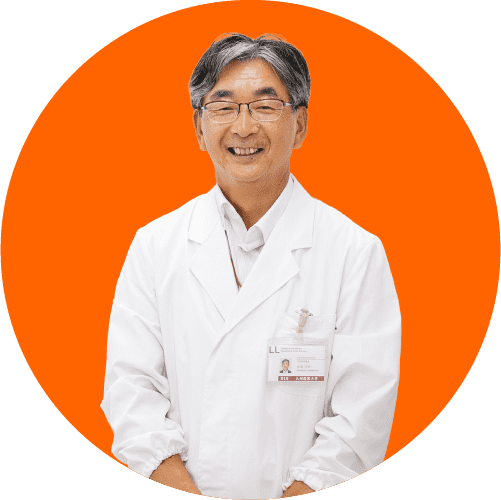
ラーメン店のおいしさを
お土産品でも再現したい -
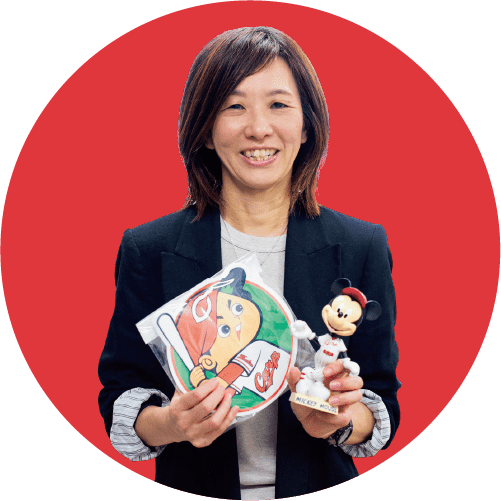
日本の観光を
もっとおもしろく変えていく -

暮らしも人間性も豊かになる
「言語学」の魅力 -
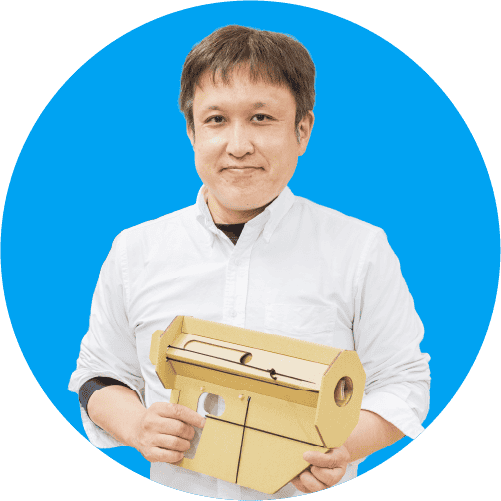
「工作」と「遊び」の力で
地域の課題を解決したい -

新興国の経済研究で
日本の経済を輝かせる -

九州から世界への挑戦を
研究を通して応援したい



