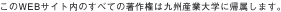科目名: ビジネス・会計課題研究1
担当者: 金川 一夫
| 対象学年 | クラス | [009] | |
| 講義室 | 開講学期 | ||
| 曜日・時限 | 単位区分 | ||
| 授業形態 | 一般講義 | 単位数 |
| 準備事項 | |
| 備考 |
| 講義の目的・ねらい(講義概要) | 今日、組織の会計担当者はつねに変化する複雑な環境で働いている。会計担当者が働く経済的な環境や法律的な環境は予想できないほど変化している。また、情報技術(IT)も驚くべき早さで進歩している。このような環境の変化に適合するように、会計担当者は経営活動についての財務・非財務の情報を提供して、解釈できることに加えて、さらに将来を予測する能力も要求されている。会計担当者が組織に価値を加えるために、会計情報システム(AIS)の設計と機能を改善する方法について研究する。ここでは、AIS研究のための研究課題を設定し、構想を検討することを目的とする。 |
| 講義内容・演習方法(講義企画) | "第1回 会計情報システム研究の意義 『基礎的会計理論(ASOBAT)』をもとに会計目的と会計情報の範囲の拡大について概説し、AIS研究の意義を説明する。 第2回 会計基準の検討 『基礎的会計理論(ASOBAT)』をもとに会計基準について討論する。 第3回 外部利用者のための会計情報の検討 『基礎的会計理論(ASOBAT)』をもとに外部利用者のための会計情報について討論する。 第4回 内部経営管理者のための会計情報の検討 『基礎的会計理論(ASOBAT)』をもとに内部経営管理者のための会計情報について討論する。 第5回 会計理論の拡張の検討 『基礎的会計理論(ASOBAT)』をもとに会計理論の拡張について討論する。 第6回 最新文献(日本)の討論(1) 会計関係学会誌のAISに関連する最新の文献について討論を行う。 第7回 最新文献(日本)の討論(2) 会計関係学会誌のAISに関連する最新の文献について継続して討論し、関連する文献を調査する。 第8回 最新文献(米国)の討論(1) 米国会計学会Journal of Information Systemsの最新の文献について討論を行う。 第9回 最新文献(米国)の討論(2) 米国会計学会Journal of Information Systemsの最新の文献について継続して討論し、研究テーマを検討する。 第10回 文献調査の指導 受講者に対して会計情報システムに関する文献調査を指導する。 第11回 文献調査レポートの検討 受講者が図書館等で調べた会計情報システムに関する文献についてレポートを提出させ、討論する。 第12回 研究テーマの検討 受講者が図書館等で調べた会計情報システムに関する文献のレポートを討論して、研究テーマを検討する。 第13回 研究構想の検討 受講者が図書館等で調べた会計情報システムに関する文献のレポートを討論して、構想を検討する。 第14回 研究方法への展開 受講者が図書館等で調べた会計情報システムに関する文献のレポートを討論して、具体的な研究目的と方法に展開する。 第15回 まとめ 総括。 " |
| 評価方法・評価基準 | 評価基準 研究の進捗度により評価する。 評価方法 期間内の報告書提出20%、最終的な研究報告書提出80% |
| 履修の条件(受講上の注意) | 受講上の注意 受講に際して、会計学と情報処理に関する基礎的な知識を前提とする。 |
| 教科書 | 適宜、論文等を配布する。 |
| 参考文献 | M.B.Romney, P.J.Steinbart,Accounting Information Systems, Prentice Hall. |
| 特記事項(その他) |