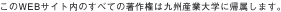科目名: 産業史研究
担当者: 加藤 要一
| 対象学年 | クラス | [005] | |
| 講義室 | 開講学期 | 前期 | |
| 曜日・時限 | 単位区分 | ||
| 授業形態 | 一般講義 | 単位数 |
| 準備事項 | |
| 備考 |
| 講義の目的・ねらい(講義概要) | 産業史をはじめ日本の歴史の通念的理解では、明治維新を大きな区切りとし、近世と近代を「非連続的」に捉えることが多い。しかし、近代以降の産業化には、江戸時代からの「遺産」が活用されたことも見逃してはならない。この科目では近世から現代にいたる日本の産業史を、「連続的」に理解するため、分野別に通史的に講義することにした。また、日本の産業化の過程を、西洋から移植された近代工業と、江戸時代から存在する在来産業の二部門の均衡成長であるという視点から、検討する。 |
| 講義内容・演習方法(講義企画) | "第1回 産業史研究の課題 産業史の対象と方法 第2回 近代経済成長 「離陸」と初期条件 第3回 制度的枠組み 貨幣、財政・金融政策 第4回 農業 在来農法と近代農法 第5回 産業構造と地域経済 産業構造の長期的概観と地域経済の構成 第6回 綿業 近代紡績業と産地織物業の発展 第7回 醸造業 需要動向、資産家・名望家論 第8回 製鉄 たたら製鉄から近代製鉄へ 第9回 機械工業 機械工業各部門の発展と生産管理・経営管理 第10回 鉄道と海運 鉄道、道路、内航海運の発達 第11回 商業 小売業と卸売商業 第12回 非農生産と資本形成 エネルギー、工業素材、生産財、消費財の各産業 第13回 労働 賃金の長期変動と労働市場 第14回 産業史研究の現段階 産業史研究の現状と課題 " |
| 評価方法・評価基準 | 研究報告、討論、提出レポートの総合評価。 |
| 履修の条件(受講上の注意) | 予習、復習をおこなうこと。 |
| 教科書 | 西川俊作、尾高煌之助、斎藤修『日本経済の200年』日本評論社 |
| 参考文献 | |
| 特記事項(その他) |